はじめに:今の「高揚感」に潜むリスクとは?
日本や米国をはじめとする世界の株式市場は、連日のように過去最高値を更新しています。資産評価額が膨らみ、懐が潤っていると感じている方も多いでしょう。評価損益を見て思わずニヤけてしまう、あるいは「今こそもっと投資をすれば、もっと儲かる!」と、さらなる投資に駆り立てられている方もいるかもしれません。
しかし、株価が「高い時」こそ、私たちは立ち止まって冷静に考える必要があります。この高揚感の裏側には、投資家が意識すべきリスクが潜んでいるからです。
本記事では、この「株価が高い時」に、あなたが「長期的な成功」を収めるために考えるべき5つの重要な行動を、伝説の投資家の言葉を交えながら解説します。
冷静になる:「貪欲」な時に「恐れ」を持て
「株価が高い時」に最も意識すべきは、感情のコントロールです。
伝説の投資家ウォーレン・バフェットは、投資の世界における人間の感情の影響について、以下のように述べています。
「繰り返し流行している恐怖と貪欲という極めて感染しやすい2つの病は、投資の世界で永遠に発生し続けるだろう。(中略)我々の目標はもっと控えめなもので、他の人々が貪欲であるときに恐れ、他の人々が恐れているときに貪欲であろうとしているだけだ」
株式市場が高値を更新し、周りの投資家たちが「もっと上がる」と楽観的で「貪欲」になっているときこそ、私たちは「恐れ」を持ち、一歩引いて冷静になる必要があります。現在の投資判断が、感情や市場の熱狂に流されていないかを自問自答しましょう。
過熱ぶりを客観的な指標で確認する
株価が高い時は、企業の「実力」以上に「将来への期待」が大きく織り込まれていることが多いです。その「期待」が過熱しすぎていないかを客観的に判断するために、以下のバリュエーション指標を確認しましょう。
投資の過熱度を測る主要なバリュエーション指標
| 指標 | 意味 | 判断の視点 |
| PER (株価収益率) | 株価が1株当たり利益の何倍かを示し、利益に対する割安・割高度を測る。 | 過去平均と比べ「割高ではないか?」 |
| PBR (株価純資産倍率) | 株価が1株当たり純資産の何倍かを示し、企業の解散価値に対する割安・割高度を測る。 | 純資産から見て「妥当な水準か?」 |
現在の主要株価指数のバリュエーション状況(参考情報)
特に、米国の主要指数であるS&P 500は、PERやPBRが過去の平均を大きく上回っており、バリュエーションの観点からは割高感が強い状況にあります。
- S&P 500のPER(例:約25倍):過去平均(約15倍)と比較して高水準。
- S&P 500のShiller P/E (CAPEレシオ):ドットコムバブル時以来の高水準とも言われ、市場の過熱を示唆しています。
一方で、日本のTOPIXは、PBRが過去平均を上回るなど、企業の資本効率の改善が見られる側面もありますが、PERが過去平均をやや上回っている点には引き続き注意が必要です。
【考えるべきこと】
高バリュエーションは、「将来の大きな利益成長」を前提としています。「この水準は、本当に将来の利益成長で正当化できるのか?」を深く考えることが大切です。
当初の投資方針を再確認する
市場が好調な時こそ、自分の投資の「軸」がぶれていないかを確認することが極めて重要です。
- 投資の目的:なぜ投資をしているのか(例:老後の資金、教育資金など)。
- 投資方針:長期投資か、短期投資か。
- 資産配分の割合:株式・債券・現金の目標比率。
- 月の投資額:積立額に変更はないか。
株価が高い時、人は「もっと儲けたい」という感情から、無計画な一括購入や、リスクの高い銘柄への集中投資に走りやすくなります。当初定めた「投資の目的と方針」に立ち返り、現在の行動がそれに沿っているかをチェックしましょう。
もし、まだ目的や方針を明確に定めていない場合は、「目標達成のために必要なリターン」から逆算して、この機会に定めることを強くお勧めします。
ポートフォリオを点検・リバランスする
株価が上昇している状況では、設定した資産配分から自然と株式の比率が増加しています。株式比率が増えるということは、ポートフォリオ全体のリスクも高まっていることを意味します。
リバランスでリスクを調整する
あなたの「リスク許容度」に対して資産配分が適正かを再確認し、目標の配分比率に戻す「リバランス」を行いましょう。これは、「守りの資産(債券・現金など)を見直す」タイミングでもあります。
リバランスの主な手法は以下の3つです。長期・積立投資家におすすめなのは、リスクを抑えつつ機会損失を防ぐ「②」です。
| 手法 | 内容 | メリット/デメリット |
| ① 株式を売却(利益確定)する | 上昇した株式の一部を売却し、現金や守りの資産に移す。 | デメリット:利益確定に課税される(NISA除く)。売却後の上昇を享受できない。長期投資の目的から逸れる可能性。 |
| ② 株式の新規購入額を減らす/やめる | 株式の積立を抑え、債券や現金の積立・保有を増やすことで、時間をかけて比率を調整する。 | メリット:税金がかからない。売却しないため、その後の上昇も享受可能。長期・積立投資家にとって最も推奨される手法。 |
| ③ 他の資産を購入し、株式比率を相対的に下げる | 株式以外の資産(債券、REITなど)を追加で購入し、全体のバランスを戻す。 | デメリット:総投資額が増えるため、リスク総額は増加する。追加資金が必要。 |
長期のインデックス積立投資を目的としている場合、積極的な売却(①)は推奨されません。株価が暴落したときの心の安心や、追加投資の余力を確保するためにも、株式の購入を抑えて現金比率を高める(②)ことを検討しましょう。
まとめ:高値の時こそ「計画通り」に
「株価が高い時」は、儲かる喜びと、さらなる上昇への期待から、最も判断を誤りやすい「危険な時」でもあります。
この状況で取るべき行動は、「より儲けるための行動」ではなく、「長期的な成功から逸脱しないための行動」です。
- バフェットに習い、冷静に「恐れ」を持つ。
- 客観的な指標で市場の「過熱ぶり」を確認する。
- 当初の投資方針を再確認し、「軸」をぶらさない。
- リバランスでリスクを管理し、次の暴落に備える。
「株価が高い時」も「株価が安い時」も、感情に流されず、あなたの投資計画通りに行動することが、長期投資の成功への最も確実な道です。
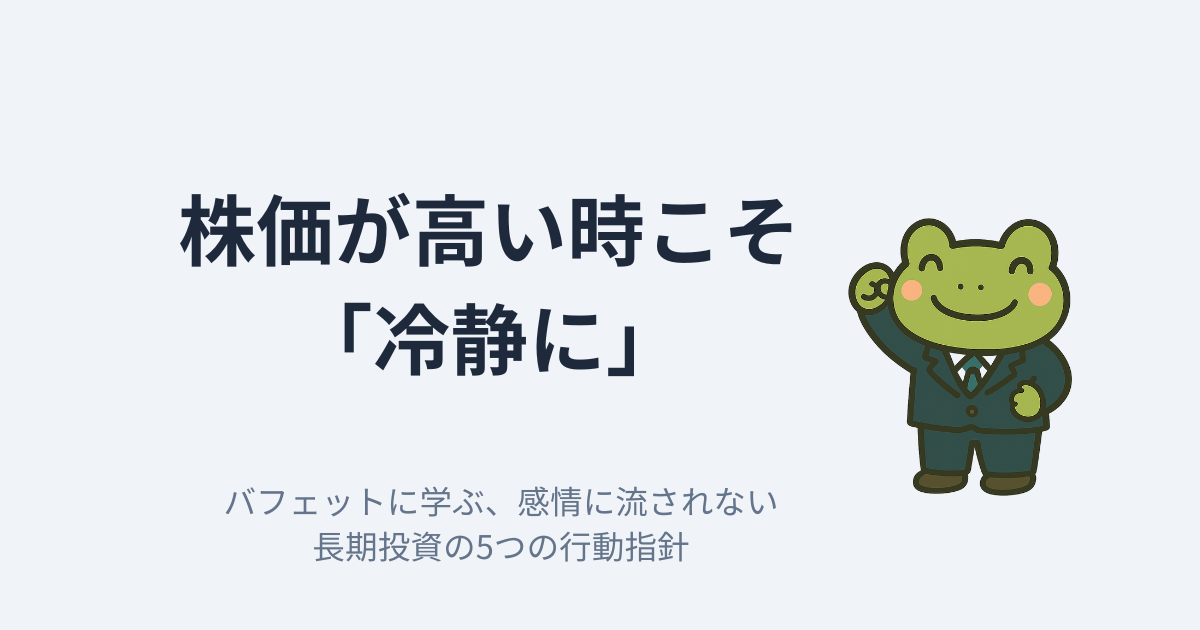
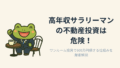

コメント