社員持株会(以下、持株会)。 多くの企業が導入しており、人事部からも加入を勧められる制度です。
「奨励金が10%も付く」「給与天引きで貯まる」といったメリットを聞くと、一見「やらないと損な制度」に見えます。
しかし、最初に結論を明確にしておきます。 私は、基本的にはおすすめしません。
なぜなら、給与(労働収入)と株(金融資産)を同じ企業に集中させる行為(=集中投資)だからです。
企業が順調なうちは、「社員であり株主でもある」という立場は心地よいものです。資産も給与も増えていきます。 しかし、ひとたび逆風が吹けば状況は一変します。
- 給与が減る(または失業する)
- 株価が暴落し、資産も同時に激減する
この「往復ビンタ(二重の打撃)」を食らうリスクがあるからです。
かつてアメリカのGM(ゼネラル・モーターズ)が経営破綻した際、多くの社員が職を失うと同時に、老後資金として積み立てていた自社株が紙切れになりました。 これは決して“過去の海外の事件”ではありません。どの会社でも、明日起こり得る現実です。
だからこそ、私は基本的に持株会を推奨しません。 ただし、「どうしてもやりたい」「会社との付き合いもある」という人に向けた、“例外的な参加基準”も存在します。
その基準はシンプルです。 「どうしてもやるなら、毎月の投資額の“5%以内”に抑えること」
理由は後述しますが、この「5%」こそが、集中リスクを抑えつつ、奨励金というメリットだけを賢く拾うための「黄金比」だからです。
本記事では、以下の順で解説します。
- 持株会のメリット(意外な副次効果あり)
- それでも絶対におすすめしない「構造的な理由」
- 最適解は「5%ルール」である根拠
- 賢い出口戦略(売り方)
持株会のメリット(まずはフェアに評価)
否定する前に、制度として優れている点も整理しましょう。主に3つのメリットがあります。
奨励金(+5〜20%)という「確定リターン」
企業によっては、積立額に対して5%〜20%程度の奨励金を上乗せしてくれます。 投資の世界で、買った瞬間に数%〜数十%の含み益が出る商品は他にありません。ここだけを見れば、確かに最強の制度です。
「経営視点」が身につき、出世に有利になる(副次効果)
これは意外と語られないメリットです。 自社株を持つと、嫌でも会社の株価や業績が気になり始めます。
- 投資家向け説明資料(IR)を読み込むようになる
- 中期経営計画の意図を理解しようとする
- 会社の収益構造や、今後の注力事業に敏感になる
その結果、「経営層と同じ視点」を持てるようになります。 上司や経営層は、常に「会社の数字」を見て動いています。この視座が合うようになると、議論の質が上がり、結果として評価や昇進にプラスに働くケースがあります。これはキャリア上の大きな武器になります。
配当や自社株買いの恩恵
「給与はあまり上がらないが、株主還元(配当・自社株買い)には積極的」という日本企業は増えています。 こうした企業に勤めている場合、労働者としてのメリットより、株主としてのメリットの方が大きい場合があり、「社員+株主」のポジションに合理性が生まれます。
他にもサラリーマンの強みを最大限に活かす方法をご紹介しています。
👉会社員こそFIREに有利な理由|住居支援・医療制度・遺族年金の特権とは
👉サラリーマンの最強節約術!ふるさと納税の仕組みと新ルール(ポイント禁止)への賢い対処法
それでも「基本的にはおすすめしない」3つの理由
メリットがあってもなお、私が推奨しないのには、致命的な欠点があるからです。
「給与」と「資産」の一極集中リスク(最悪のポートフォリオ)
投資の基本は「分散」です。 しかし持株会は、あなたの人生のリソースを「たった1社」にフルベットする構造を強制します。
会社の業績が悪化すれば、ボーナスカットやリストラ(給与減)と、株価下落(資産減)が同時に襲ってきます。 生活防衛資金が必要な時に限って、資産価値も下がっている。これが持株会の最大の怖さです。
👉自社株に偏ると「給与も資産も同じ会社に依存する」状態になり、非常にリスクが高いです。
集中投資を避ける理由については、株価予測が難しい理由と分散投資の大切さで詳しく解説しています。
NISAが使えず、税制不利
現在の資産形成の王道は「新NISA」を使ったインデックス投資です。 しかし、持株会は基本的にNISA口座(非課税)では買えません。 利益が出ても約20%の税金取られる「課税口座」での運用になります。非課税枠という最強の権利を捨ててまでやる価値があるか、疑問が残ります。
👉代替策としては、NISAを活用して投資信託に分散投資するのが王道です。購入の手順や商品選びの考え方については、NISAで買うならこの投資信託をご覧ください。
👉投資商品の種類と特徴を初心者向けに解説|失敗しない選び方とおすすめ商品例
売りたい時にすぐ売れない(流動性の低さ)
一般的な株式投資のように、スマホで「今すぐ売却」ボタンを押して現金化、というわけにはいきません。 退会や引き出し手続きに時間がかかったり、インサイダー取引規制の期間中は売買できなかったりと、「逃げたい時に逃げ遅れる」リスクが高い資産です。
👉流動性の重要性はNISAとiDeCo、どちらを優先すべき?でも触れています。
どうしてもやりたいなら「投資額の5%」まで
では、「奨励金は欲しい」「付き合いで入らざるを得ない」場合はどうするか。 私が提案する最適解はこれです。
■ 推奨ライン:毎月の資産運用額の「5%以内」
例えば、毎月10万円を投資に回せる人なら、持株会は「月5,000円」まで。 残りの9万5,000円は全世界株(オルカン)などのインデックス投資へ。
明確な数式があるわけではありませんが、この「5%」は非常に合理的なラインです。
- リスク制御: 万が一会社が倒産しても、資産全体のダメージは軽微(5%未満)。
- メンタル維持: 株価が下がっても「まあ、月数千円の話だし」と笑って流せる。
- メリット享受: 奨励金という「美味しい部分」だけは確実に拾える。
これ以上比率を高める必要はありません。 持株会は、全世界株のように「国・通貨・企業」が分散された資産ではなく、個別株です。長期的にインデックス投資に勝ち越す可能性は低いのが現実です。
最適な使い方(制度は“おまけ”として扱う)
持株会を利用する場合の「鉄の掟」を3つ授けます。
- 最小限の金額(一口)で参加する 奨励金目当てなら、最低金額(例:数千円)で十分です。
- 単元株(100株)になったら即引き出して売却 ここが重要です。多くの持株会は「100株」貯まらないと個人の証券口座に移せません。 「100株貯まる → 即座に個人の証券口座へ振替 → 売却」を繰り返してください。 持株会に「長期投資」や「愛社精神」は不要です。あくまで「奨励金を現金化する装置」と割り切りましょう。
- コア資産は「全世界株」で作る あなたの資産形成の柱は、あくまでNISA口座でのインデックス投資です。持株会はあくまで「サブ(お小遣い稼ぎ)」の位置付けを崩さないでください。
まとめ
- 結論: 持株会は「集中投資リスク」が高すぎるため、基本的にはおすすめしない。
- 例外: どうしてもやるなら、毎月の投資額の5%以内(月10万円投資なら5,000円)に抑える。
- 戦略: 最小額で積立し、単元株(100株)が貯まり次第すぐに売却して、全世界株式などの優良資産に買い換える。
会社と心中する必要はありません。 自分の資産と未来は、会社任せにせず、自分自身でコントロールできる「分散されたポートフォリオ」で守りましょう。
📈 長期でコツコツ資産を増やしたいなら
楽天証券は投資信託の積立が充実していて、ポイント投資も可能です。
インデックス投資を始めるなら、まず口座を作っておくのがおすすめです。
👉 [楽天証券の口座開設はこちら]※リンクはアフィリエイトを含みます。
※本記事には広告リンクを含みます。投資にはリスクがありますので、最終判断はご自身の責任でお願いいたします。
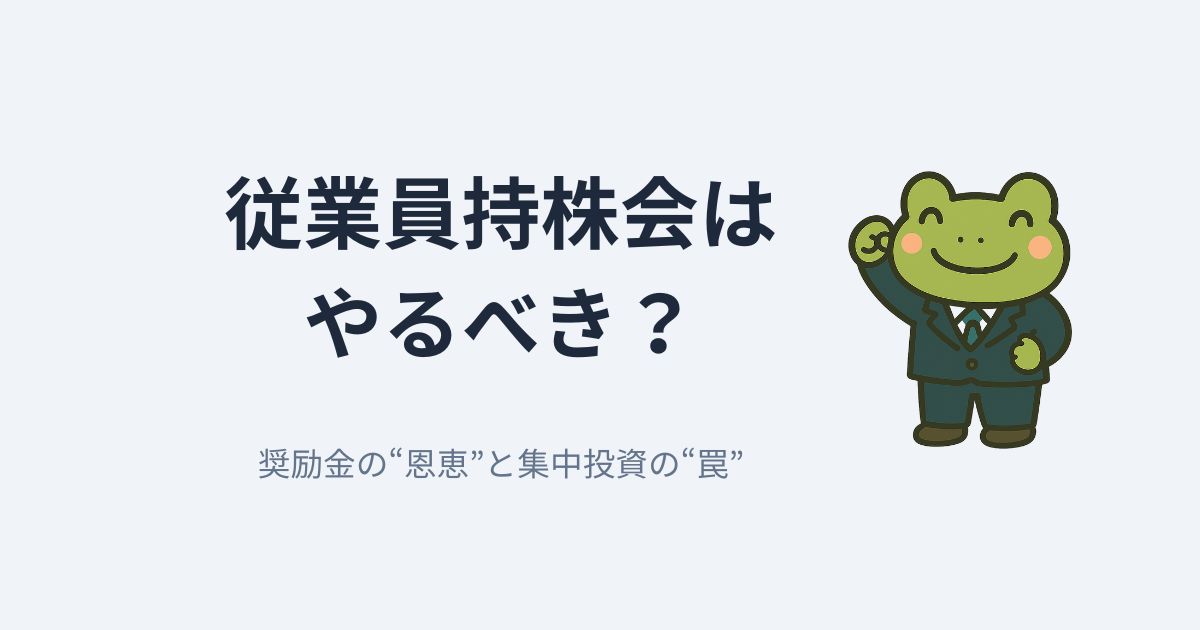
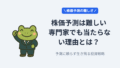

コメント