#自由になるためのお金の話
このブログでは、「サラリーマンからでも経済的自由を目指せる」方法を、実体験とともに発信しています。
1. 教育方針を最初に決めるべき理由
教育費は人生の三大支出のひとつでありながら、最も「感情的になりやすい」分野でもあります。
特に中学受験は「周囲がやっているから」という理由で始めてしまうケースが後を絶ちません。
しかし、教育費は家計へのインパクトが大きいため、「我が家の教育方針」を明確にし、それに基づいた投資であるべきです。
- 中学までは公立、大学進学は奨学金を使うか否か、などを決めておく
- 子どもが中学生以降になったら、本人と一緒に方針を話し合う
- アメリカで社会問題になっている「大学ローン地獄」を他人事としない
2. 教育費はいくらかかるのか?(文部科学省データ)
| 教育段階 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|
| 幼稚園(3年間) | 約66万円 | 約158万円 |
| 小学校(6年間) | 約193万円 | 約959万円 |
| 中学校(3年間) | 約144万円 | 約423万円 |
| 高校(3年間) | 約137万円 | 約290万円 |
| 大学(4年間) | 約542万円 | 約778万円(私大文系平均) |
👉 オール公立:約1,000万円、すべて私立:約2,500〜3,000万円
👉 子どもが2人いれば倍。早めに見通しを立てて備えることが重要です。
教育費の大部分は「学校外活動費」
文部科学省の最新調査(令和5年度子供の学習費調査)によれば、学校外活動費の構成比は以下の通りです。
| 教育段階 | 学校外活動費の割合(公立) |
|---|---|
| 幼稚園 | 約54% |
| 小学校 | 約64% |
| 中学校 | 約65% |
| 高校 | 約41% |
特に習い事や塾費用が家計を圧迫するため、どの習い事に・いくら・何個通わせるかをコントロールすることが教育費対策のカギです。
3. 高校・大学の無償化制度を活用しよう
✅ 高校無償化(高等学校等就学支援金)
年収590万円未満の世帯を対象に、私立高校の授業料も最大年約39万円まで補助される制度です。
対象世帯は年収によって異なるので、詳細は文科省のリーフレットをご覧ください。
✅ 高等教育就学支援制度(大学)
住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯には、授業料の減免+給付型奨学金の支援が受けられます。
大学進学の経済的ハードルは以前より確実に下がってきています。
詳細はこちら → 文科省:高等教育就学支援制度
4. 教育費をどうやって貯めるか?
- 短期(~5年以内):預金が基本。株式は避ける
- 長期(10年以上):投資も一部活用可能。つみたてNISAやジュニアNISAなど
特に大学進学資金を5年以内に使う予定なら、株価下落で資金が足りなくなるリスクを避けるため、運用せずに確実に貯めるのが賢明です。
5. 私の実体験からのアドバイス
- 我が家も中学受験塾に通いましたが、途中で退塾。本人の気持ちや成長段階も考慮して冷静な判断を
- 周囲に流されて小中高すべて私立にしている家庭が、生活に苦しんでいるケースも多い
- 兄弟がいる場合、片方だけ私立に行かせるのが難しいため、支出が倍になることも
6. 将来設計に役立つライフシミュレーターの活用
金融庁が公開しているライフプランシミュレーターを活用して、教育費・住宅・老後資金まで長期的に試算してみましょう。
無料配布されているエクセルでもいいと思います。
「教育費=不安」ではなく、「先読みできる支出」と捉えることで、冷静な準備ができます。
まとめ
教育費は“かけすぎ”に注意が必要です。
不安をあおる情報もありますが、制度の活用や習い事のコントロールをすれば、恐れることはありません。
公的制度も年々充実してきています。焦らず、家庭に合った方針を定めて、長期的にコツコツ備えることが大切です。
「家計と将来の見通しを持って備える」ことが、子どもと家庭の未来を守る第一歩です。
関連記事もチェック!
✅ 共働き夫婦の家計はどう分担する?我が家のリアルな家計管理術
👉 共働きなのにお金が貯まらない?家計のブラックボックス化を防ぐコツを紹介!
✅ 家計簿をつければ人生が変わる!社会人1年目からのマネー習慣
👉 すべては「見える化」から。教育費の備えもまずは家計簿から!
#自由になるためのお金の話
このブログでは、「サラリーマンからでも経済的自由を目指せる」方法を、実体験とともに発信しています。
▼noteでもFIREに関する実体験を連載中です。
👉 noteアカウントはこちら
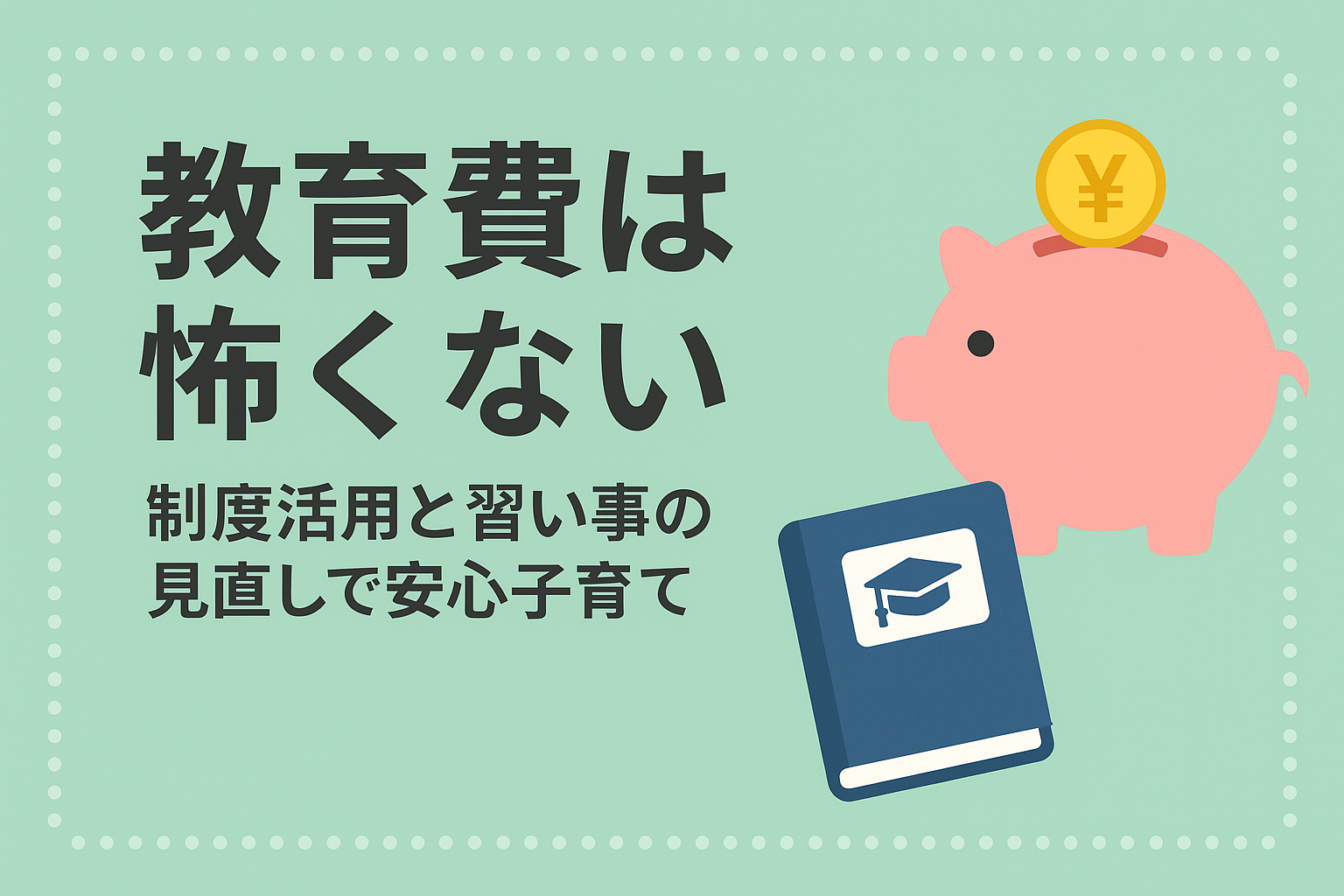


コメント