年末が近づくと、会社員にとっての一大イベントが「年末調整」です。この時期、生命保険会社などから送られてくる控除証明書を見て、「今年はどれくらい還付されるかな?」と楽しみにしている方も多いでしょう。
しかし、単に書類を提出して終わりにするのはもったいない! 年末調整は、あなたが加入している「保険」を見直し、将来の資産形成を加速させる絶好のチャンスです。
本記事では、生命保険料控除の基本を正しく理解し、その上で「控除のためだけの追加加入」がいかに無意味か、そして「あなたの保険を見直すべき理由と具体的な方法」について、踏み込んで解説していきます。
控除制度の基本:生命保険料控除と地震保険料控除
年末調整の際に申告できる保険に関する所得控除は、主に生命保険料控除と地震保険料控除の2つです。
生命保険料控除とは
納税者が生命保険料、介護医療保険料、および個人年金保険料を支払った場合、その金額に応じて所得から一定額が控除される制度です。所得控除が適用されると、課税される所得が減るため、結果として所得税や住民税が安くなります。
💡 現行の生命保険料控除(新制度)の3つの区分
現行制度では、保険の種類に応じて以下の3つの区分があり、それぞれで控除額が計算されます。
- 一般生命保険料控除(旧制度の一般保険に相当)
- 対象となる保険: 終身保険、養老保険、学資保険などの死亡・生存を事由とする保険の基本契約部分。
- 介護医療保険料控除(新制度で新設)
- 対象となる保険: 医療保険、がん保険、介護保険など、入院や手術、所定の要介護状態などに伴う給付金が支払われる部分の保険料。
- 個人年金保険料控除(旧制度の個人年金保険に相当)
- 対象となる保険: 税制適格の要件(年金受取人が契約者または配偶者であること、保険料払込期間が10年以上であることなど)を満たした個人年金保険。
| 区分 | 控除限度額(各区分ごと) |
| 所得税 | 最大 4万円 |
| 住民税 | 最大 2.8万円 |
これら3区分の控除は併用が可能ですが、生命保険料控除全体での合計控除額には上限が設けられています。
- 所得税の最大控除限度額: 12万円
- 住民税の最大控除限度額: 7万円
詳細は国税庁のウェブサイトをご参照ください:
地震保険料控除について
地震や噴火、津波を原因とする損害により保険金が支払われる地震保険の保険料が対象となります。また、2006年以前に契約した一定の旧長期損害保険も対象となる場合があります。
- 所得税の最大控除限度額: 5万円
- 住民税の最大控除限度額: 2.5万円
誰も教えてくれない!控除額に関する決定的な勘違い
ここで、多くの人が誤解しがちな「控除」の仕組みについて、正しく理解しておきましょう。
🚨 勘違い:控除額=還付される金額ではない!
「生命保険料控除で4万円控除されるから、4万円戻ってくる!」と思っていませんか? これは間違いです。
控除とは、税金が計算される対象の所得(課税所得)を減らすことであり、戻ってくる金額(還付金)ではありません。実際に戻ってくるお金は、「控除額」にあなたの「税率」をかけた金額です。
還付される金額 = 所得控除額 × あなたの税率
💰 計算例
例えば、あなたが年間2万円の生命保険料を支払い、所得税率が20%だとしましょう。
- 控除額の確認: 仮に控除額が2万円だったとします(※実際の控除額は年間保険料と計算式で決まります)。
- 還付額の計算: 20,000円(控除額)× 20%(所得税率) = 4,000円
この場合、戻ってくるお金はたったの4,000円です。
控除の恩恵は、「あなたが支払っている税率」によって大きく左右されます。この事実を知ると、単に「控除があるから」という理由で保険に入ることのコスパが、いかに悪いかが分かってくるはずです。
「控除枠の穴埋め」を勧めるセールスに騙されてはいけない!
年末調整の時期、保険会社や銀行の窓口で、こんなセールスを受けたことはありませんか?
- 「お客様は『介護医療保険料控除』の枠が余っています。ここに加入すれば、実質負担ゼロで控除が受けられますよ!」
- 「あと数千円の保険料を支払うだけで、最大の控除額が受けられますよ!」
結論から言います。控除のためだけに新たな保険に加入することは、絶対に推奨できません。
控除によるメリットは、コストに見合わない
例えば、所得税・住民税の合計の最大控除額は、合計19万円(所得税12万円+住民税7万円)です。もしあなたが最高税率(所得税45%+住民税10%)だとしても、戻ってくるお金の最大額は、
所得税:120,000 × 45% = 54,000円
住民税: 70,000 × 10% = 7,000円
年間合計 = 61,000円
年間最大6.1万円のメリットのために、数十万円の保険料を払い続けることになります。
一方で、保険会社や販売員は、あなたが支払う保険料から多額の手数料を受け取っています。彼らにとっての利益(コスト)は、あなたが受け取る控除額のメリットを遥かに上回っているのが実情です。
日本の「公的制度」が強力な盾になっている事実
私たちが民間保険に入る目的は、「万が一」のリスクに備えることです。しかし、日本には世界に誇れる非常に充実した公的制度があります。
- 医療費: 高額療養費制度により、ひと月の医療費自己負担額には上限が設けられています。自己負担が青天井になることはありません。
- 年金: 公的年金(厚生年金・国民年金)が老後の生活基盤を支えます。
- 介護: 公的介護保険(40歳以上)があり、自己負担は原則1割~3割です。
基本的な戦略は、「公的制度でカバーしきれない部分」+「個人の貯蓄・投資」で備えることです。
民間保険会社を介するということは、保険料に彼らの「手数料」「人件費」「利益」といったコストが上乗せされることを意味します。これらのコストは、すべてあなたの負担です。公的制度と貯蓄で備える方が、圧倒的に効率的であなたの資産が守られます。
こちらもご参考にしてください。
👉生命保険は本当に必要?──入る前にまず見直すべき「公的保障」と自分の家計
👉医療保険はいらない?会社員が入らなくても安心できる理由
保険料控除で見つけた保険は「解約・見直しのチャンス」!
年末調整の書類で、あなたが加入している保険の種類が明らかになります。これは、「この保険は本当に必要か?」と、ご自身の保険ポートフォリオを見直す最大のチャンスです。
私が考える、多くの人にとって不要な保険と、その見直し先は以下の通りです。
貯蓄型保険(終身保険、養老保険、学資保険)を解約しよう
これらの保険は「保険」と「貯蓄」が混ざった商品で、貯蓄部分にかかるコストが高く、利回り(資産の増え方)が非常に悪いです。
- 推奨アクション:解約し、解約返戻金を全額、貯蓄や投資信託へ切り替えましょう。
- 資産形成: NISA(新NISA)やiDeCo(イデコ)などの税制優遇制度を活用した投資(インデックスファンドなど)へ。
- 本当に必要な保険: 死亡保障が必要なのは、一家の稼ぎ頭で、かつ扶養家族がいる期間のみです。これは、保険料が格安な「掛け捨ての定期生命保険」で必要最低限の金額をカバーすれば十分です。
医療保険、がん保険は基本的に不要
前述の通り、日本の高額療養費制度のおかげで、治療費が青天井になる心配はありません。
- 推奨アクション:解約し、毎月払っていた保険料を「貯蓄」に回す。
- 「病気になったら困る」という不安は、「生活防衛資金」(最低でも生活費の6ヶ月分〜2年分)として銀行預金に確保しておくことで解消できます。この貯蓄から、入院時の差額ベッド代(自分で選んだ場合)や、食費などを賄いましょう。
- 高額な治療費は自己選択: ほとんどのケースで、高額な自由診療は自分で選ばない限り発生しません。
個人年金保険も不要
低金利時代において、個人年金保険の利回りは非効率です。「年金」という名前の通り、老後の資金準備が目的ですが、これを民間保険に任せる必要はありません。
- 推奨アクション:解約し、NISAを活用した投資と貯蓄に切り替える。
- 効率的な老後資金形成: NISA(つみたて投資枠・成長投資枠)やiDeCoなどの非課税制度を利用し、世界経済全体に投資するインデックスファンドなどで積み立てる方が、長期的には遥かに大きな資産形成効果が期待できます。
まとめ:自分の財布を潤す施策を考えよう
年末調整での保険料控除の申請は、あなたがどんな保険に、いくら支払っているかを認識する、年に一度の貴重な機会です。
私自身、生命保険料控除を申請する保険は現在、全くありません。それは、公的制度を深く理解し、長期的な備えを「投資」と「貯蓄」の組み合わせで事前に確保しているからです。
保険料控除のメリットはごくわずかであり、そのメリットを追いかけるあまり、手数料の高い民間保険に入り続けることは、あなたの長期的な資産形成の妨げになります。
保険会社を儲けさせるのではなく、自分の財布を潤す施策を考えましょう。
- 自分の保険の目的を再確認する。
- 公的制度のカバー範囲を理解する。
- 不要な貯蓄型・医療保険を解約し、資金を投資・貯蓄へ振り分ける。
この年末調整を機に、一つ一つの保険の目的と必要性を再検討し、あなたの未来の資産を守るための最善の行動を取りましょう。
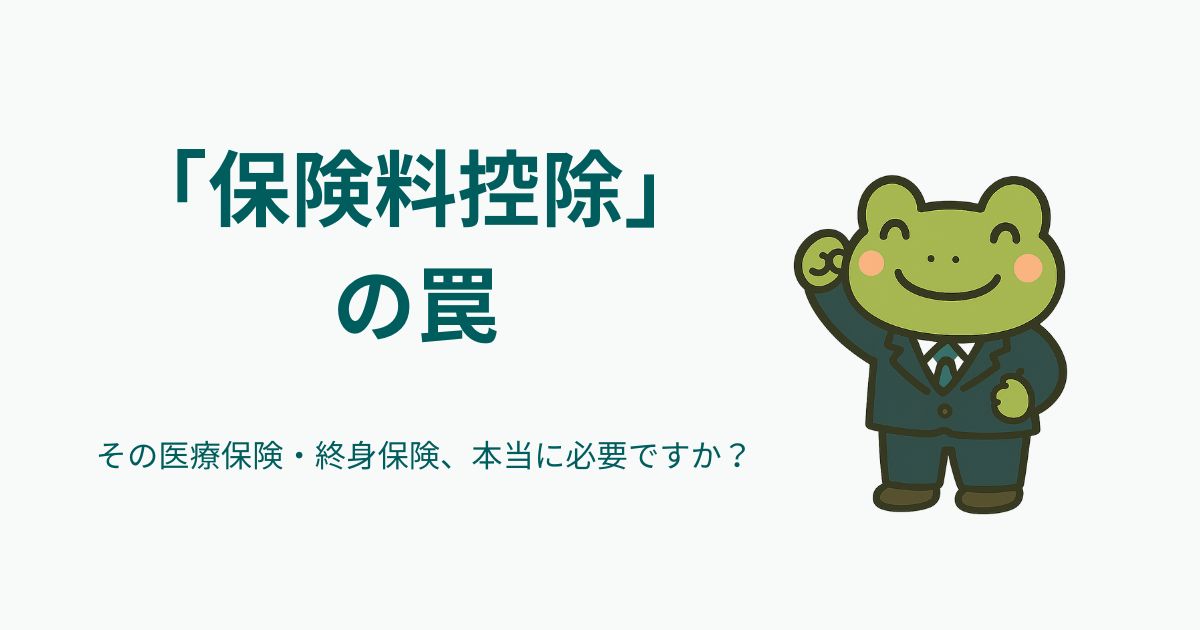


コメント