2024年、「みんなで大家さん」を運営する共生バンクが、投資家への支払い遅延や資金繰り悪化の報道で大きな注目を集めました。
「安定した家賃収入」「利回り6%保証」といった魅力的な言葉に惹かれ、数万人もの個人投資家が参加していたとされる本件は、私たちに投資の本質と現代の金融リテラシーについて、改めて深く考える機会を与えています。
「なぜ人は“高利回り”に惹かれるのか?」 「適正なリターンとは何か?」
投資の本質を見失うと、魅力的に見えるリターンの裏に潜むリスクに気づけなくなります。今回は、この事件を一つの教訓とし、投資家が持つべきリスク感覚と、大切な資産を守る姿勢について深く掘り下げて考えてみましょう。
適正なリターンを知ることの重要性
経済合理的に考えると、リターンとリスクは常に表裏一体です。
それにもかかわらず、投資の世界では「高利回り・低リスク」といった、理論的に矛盾した言葉が横行しがちです。
現在の日本の低金利環境(国債利回りがほぼゼロ)において、安定的に6%や7%のリターンを出すことは、理論的に極めて困難です。
その不自然さを理解するために、主要なアセットクラスの一般的な利回り水準を確認してみましょう。
主要アセットクラスの利回り(分配金・配当利回り)の目安
| 資産クラス | 一般的な利回り水準の目安 | リスク水準の目安 |
| 日本国債(債券) | 0%〜1%未満 | 低い |
| 日本株式(東証プライム全体) | 2%〜3%台 | 中〜高 |
| J-REIT(リート) | 3%〜4%台 | 中 |
| 「みんなで大家さん」の提示利回り | 6%〜7% | 極めて高い(隠された) |
注:上記は特定の時点での数値ではなく、一般的な傾向を示す目安です。リートは直近で4%台が高水準として評価されています(2025年9月末時点の市場平均は約4.6%)。
この表からも明らかなように、低リスクの代表である国債の利回りがほぼゼロに近い中で、「みんなで大家さん」が提示していた6%〜7%という数字は、市場の常識からかけ離れています。
もしそんな投資が本当に存在し、低リスクで安全であるならば、世界中の年金基金や機関投資家が殺到しているはずです。にもかかわらず、それが「個人でも簡単に買える」と宣伝されている時点で、私たちは不自然さに気づくべきでしょう。
投資家がまず身につけるべきなのは、「この利回りは、現在の金利環境や景気動向に照らして極めて妥当か?」という冷静な視点です。
適正なリターンを理解するとは、つまりリスクの「代償」として得られる利益の範囲を見極める力を持つことです。その妥当性の検証こそが、最初の金融防衛線となります。
適正なリスク管理姿勢とは何か
リスクを完全に避けることはできません。しかし、リスクを「理解して、意識的に引き受ける」ことはできます。本来の投資とは、このリスクを引き受けた見返りとしてリターンを得る行為です。
一方で、多くの人は「元本保証」「安定運用」という、“安心感”を与える言葉に惹かれ、リスクを直視しないまま投資をしてしまいます。
しかし、リスクが“ない”ように見える投資ほど、実は構造的なリスクが深く隠れているものです。
「みんなで大家さん」のように、仕組みが複雑で、実体(投資対象や資金の流れ)が見えにくい商品ほど、投資家にとっての最大のリスクは「仕組みを完全に理解できないこと」そのものにあります。
健全なリスク管理とは、「何が起きたら、どのような理由で損をするのか」を自分の言葉で説明できる状態を指します。それができない投資には、どんなに高い利回りが提示されていても、距離を置くべきです。
低金利が生む 「リスクテイクの暴走」
米投資家ハワード・マークスは、この現代の状況を的確に表しています。
“When safe investments offer meager returns, investors take on greater risk in pursuit of better returns – often without understanding the full implications.”
(安全資産の利回りが低下すると、人々はより高いリターンを求めてリスクを過剰に取るようになる。しばしば、その意味を理解しないままに。)
まさに今の時代です。超低金利のもとで、預金しても資産は増えません。「このままでは将来が不安だ」という焦燥感が、人々を“少しでも高い利回り”を求める行動へと駆り立てるのです。
問題は、この過程で「投資」と「投機」の境界が曖昧になることです。
本来の投資は、企業や不動産の将来価値を見極めて資本を配分する行為です。しかし、金利が極端に低い状況では、「他人より早く高利回り案件を見つけること」自体が目的化し、情報非対称性を突く“投機”の世界に足を深く踏み入れてしまいがちになります。
その結果、「儲かる話」に群がる心理が蔓延し、実態を伴わないスキームが流行する。「みんなで大家さん」も、その一つの帰結だったと言えるかもしれません。
低金利・流動性の供給が生む「不安」と「格差」
このリスクテイクの背景には、リーマンショック以降の各国中央銀行による長期的な金融緩和があります。世界は「超低金利・過剰流動性」の時代に突入しました。
市場に大量に供給された資金は、株、不動産、仮想通貨などへ流れ込み、資産価格を押し上げました。結果として、労働所得しか持たない人々と、資産を保有している層との格差が拡大しました。
「資産を持たなければ取り残される」という構造的な不安は、この低金利と金融緩和の副作用です。この焦りが、冷静さを欠いたリスクの高い投資へと人々を駆り立てる心理を生み出しているのです。
「お金を守る」ことの重要性、バフェットの教え
投資の本質は「増やす」ことにあるように見えますが、実は「守る」ことにあります。
ウォーレン・バフェットの有名な言葉は、この姿勢の重要性を的確に示しています。
「ルール1:お金を失うな。(生き抜くこと)ルール2:ルール1を忘れるな。」
長期的に資産を築いた人々は、派手な儲け話ではなく、大きな損を避けることに一貫して慎重でした。彼らは「何に投資するか」よりも、「何に投資しないか」を明確にしています。
“お金を守る”とは、単に現金を抱え込むことではありません。
- 理解できない投資に手を出さない
- 資産全体のバランスを保つ(一極集中を避ける)
- 急な儲け話に飛びつかない
この3つを徹底するだけで、多くの人が金融トラブルを回避できます。資産形成とは、負けないことの積み重ねによって築かれるものです。
おわりに:冷静な“金融防衛力”を持つ
「みんなで大家さん」問題は、単なる一企業の不運の話ではありません。
それは、低金利と資産インフレの時代における投資家心理の歪み、そして「過剰なリターンを求める社会」の構造的な問題の象徴でもあります。
これからもAI投資、不動産クラウドファンディング、暗号資産など、新しい形の投資話は次々と現れるでしょう。しかし、「リスクを理解しないままのリターン追求」は、形を変えても必ず同じ結末を迎えます。
私たちがすべきは、常に冷静に「適正なリターン」を見極め、「お金を守る」姿勢を持ち続けることです。
高リターンを求めるよりも、経済の構造や金融政策の流れを理解し、情報に踊らされない、自分自身の判断軸、すなわち金融防衛力を高めることが最良の投資です。
これが、「みんなで大家さん」騒動が私たちに残した、最も重要な教訓ではないでしょうか。
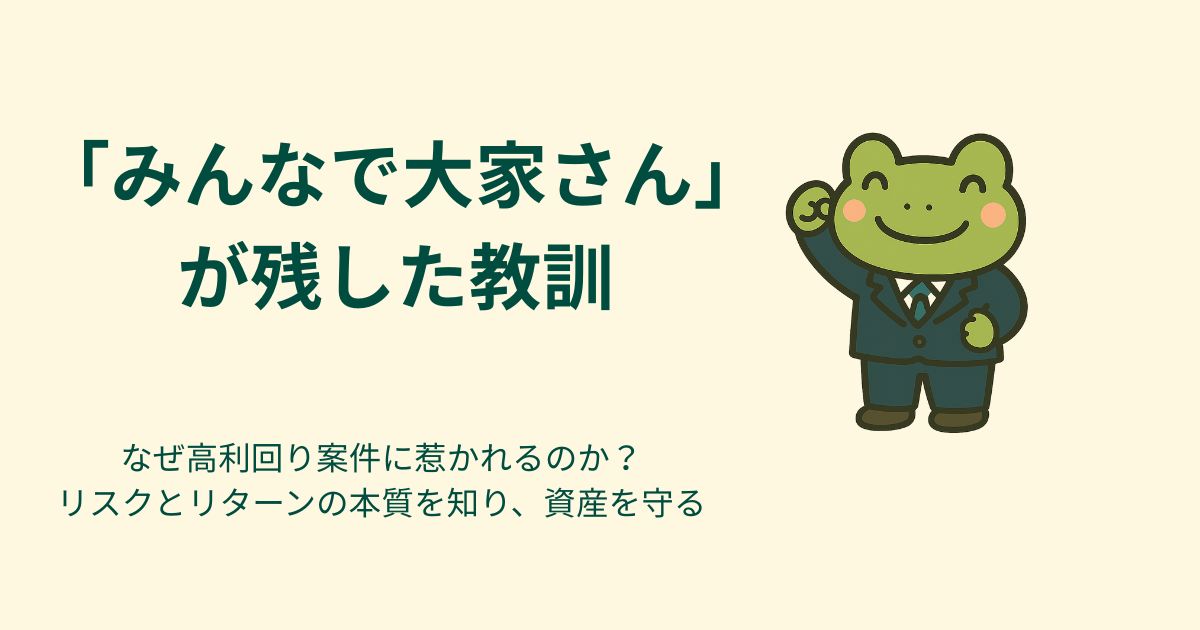


コメント