はじめに
生命保険、なんとなく入っていませんか?
私自身は、社会人になったときから「保険には基本的に入らない」と決めていました。
それは、公的保障(遺族年金など)でかなりの部分がカバーできるとわかっていたからです。
一方、僕の周りでは「毎月2〜3万円の貯蓄型保険をずっと払い続けて、身動きが取れない」と悩んでいる人が少なくありません。この記事では、そうした方に向けて、保険に入る前に絶対に確認すべきポイントを解説します。
「なんとなく不安」で契約しない
生命保険に入ってしまう理由の多くは、**「不安」**にあります。
「万一のことがあったらどうしよう」と思う気持ちはわかります。ですが、その不安は冷静に分解し、**制度や家計でカバーできるか?**を見直すことで、かなり軽減されます。
不安を煽るのが、営業トークの常套手段です。
誰かに相談するにしても、保険を売る立場にある人の言葉には注意が必要です。
公的保障だけでどれくらいカバーできるのか?
生命保険の前に、まずは国の制度(遺族年金)でどこまで守られているのかを知ることが大切です。以下の表は、夫(会社員)が亡くなった場合に遺族が受け取れる年間の年金額の目安です。

- 遺族基礎年金(子どもがいる世帯向け):約83万円+子ども1人約24万円/年
- 遺族厚生年金(会社員):平均月5〜10万円ほどが上乗せされます
たとえば月収30万円の会社員で配偶者と子供2人なら、
遺族基礎+厚生年金で月額約14万円が遺族に支給されます。これだけでも、住居費などを除けば生活は成り立つ可能性があります。
計算条件等
- 死亡した夫または妻の厚生年金への加入期間を25年(300月)とし、平成15年4月以降の加入期間がすべて該当するものとして計算しています。
- 子どもは「18歳の年度末を迎えていない」前提で、遺族基礎年金の支給対象となると仮定しています。
- 遺族厚生年金の年額は以下の式で計算:
平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 300月 × 3/4
※平均標準報酬額は厚生年金加入期間中の平均月収をもとに計算 - 加入月数が300月に満たない場合でも、300月として算定される特例があります。
- 年金額は2025年度の金額を参考にしています。将来的に物価等の影響により改定される可能性があります。
- 遺族年金(基礎・厚生ともに)に所得税・住民税・社会保険料は課税されません。
- 最新の情報は【日本年金機構の公式サイト】をご確認ください。
共働きなら、さらに安心材料がある
パートナーが正社員で月収30万円なら…
遺族年金(約14万円)+配偶者の収入(30万円)=月44万円以上の収入が維持される可能性あり。
→ 年収換算で500~700万円ほどの保障が、公的・企業制度を通じて得られています。
つまり、共働きであれば「生命保険なしでも死後生活が回る」ケースは少なくありません。
「保障」が必要な期間は意外と短い
保険が必要な時期は「万一があった場合に、家族が困る期間」です。
特に小さいお子さんがいる場合、「子どもが成人するまで」が主なリスク期間となります。
つまり、ずっと保障が必要なわけではなく、一定期間だけの備えでよいということです。
この場合は、終身保険や貯蓄型ではなく、掛け捨ての定期保険が合理的です。
周囲に多い「貯蓄型保険で後悔している人」
僕の知人には、毎月3万円の貯蓄型保険を10年以上払い続けている人がいます。
しかし、保険料の返戻率は110%程度で、資産運用としても非効率。
その間に住宅ローンや教育費が重なり、家計が回らなくなって解約……でも返戻金は少ない、という事態に陥っています。
保険料は「固定費」。長期でみると無視できない支出に
- 平均年間保険料:35.3万円(生命保険文化センター2024)
- 30年払い続けると総額:1,059万円!
このお金を年利5%で運用すれば 約2,500万円の資産に増えます。
この差は、将来の選択肢や精神的余裕の大きさにも直結します。
生命保険に頼る前にやるべき3つのこと
- 公的保障を把握する(遺族年金など)
- 貯金や資産運用でリスクに備える
- 家計の見直しで保険に頼らない余裕をつくる
これらを行った上で、どうしても不足部分を保険で補う──という順番が理にかなっています。
まとめ|僕はこう考えて保険に入っていません
僕は保険を「最後の手段」と考えています。
すでに公的保障があり、共働きで貯金もできている今、わざわざ民間保険でお金をロックする理由はないと判断しています。
一方で、万一に備えたい人が「保険を使う」のはアリです。
でもそれは、「本当に必要な保障だけを、安く・短期間で」加入するのが鉄則です。
🔗 関連記事
自由になるためのお金の話
このブログでは、「サラリーマンからでも経済的自由を目指せる」方法を、実体験とともに発信しています。
▼noteでもFIREに関する実体験を連載中です。
👉 noteアカウントはこちら
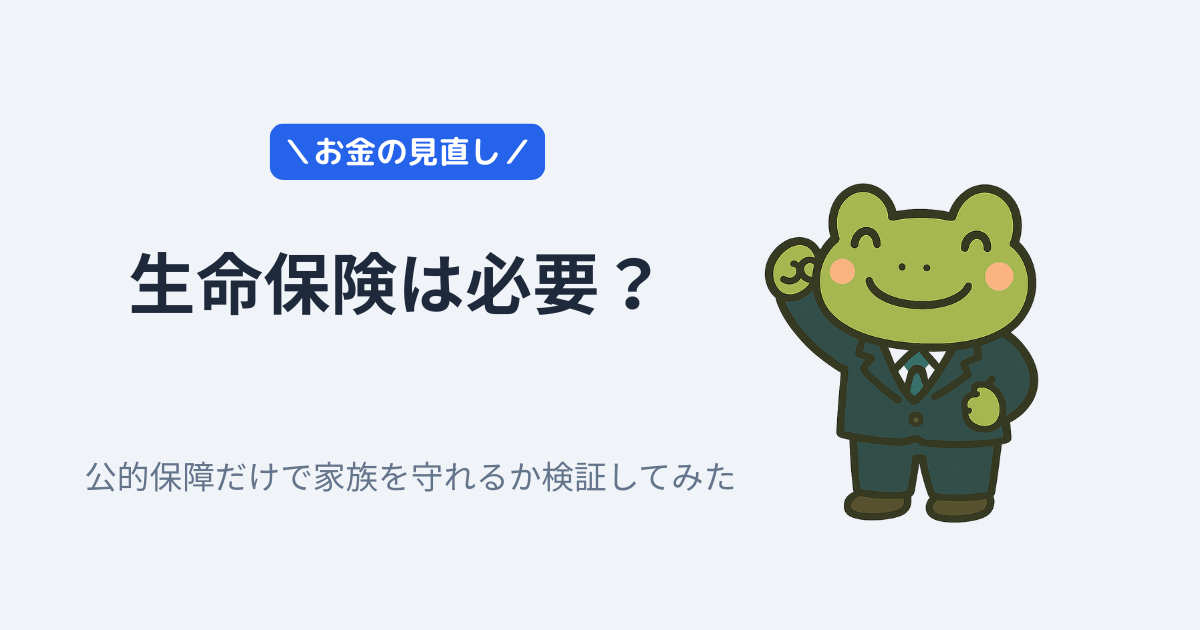


コメント